
| 蒐 書 記 |
Libris novitas lenocinatur 新奇さは書物に魅力を與ふ

篠原資明 『ベルクソン―<あいだ>の哲学の視点から』(岩波新書 2006年)
清水徹 『ヴァレリー――知性と感性の相剋』(岩波新書 2010年)
ともに20世紀を代表するフランス思想家に関して、「岩波新書」ではじめての書き下ろしなので、いくらか期待して手に取った。思想家の名前を正面に打ち出して新書とするからには、それなりの力量と見識が必要とされるはずだからである。しかし両者を通して痛感したのは、質の高い新書(しかも優れた思想家を標題に冠した新書)を作るのがいかに難しいかということであった。
『ベルクソン』は、ベルクソンの思想の概略を示すというよりは、ベルクソンを引き合いに出しながら、著者自身の関心を正面に打ち出すものであって、およそ新書的な性格とはなじまない。著者のこれまでの展開と副題を見ただけでそのことは予想できるといえばそうなのだが、実際はまさにベルクソンを理解するという視点からは大幅に外れるものとなった。ベルクソンを解説するくだりでも、著者独自の用語が織り込まれ、それがけっして巧みと言えるようなものではないので、かえって理解が阻まれる。ただ、稲垣足穂を導入して、機械的なものと有機的なものと相関と逆転を図る工夫には共感を覚えた。とはいっても、そうなると今度はベルクソンを置き去りにして、足穂論に傾いてしまうような論調を見せるので、それはやはり感心しない。最後はマザー・テレサ礼讃と「即身成仏論」に終わると言えば、その雰囲気は推測できるかもしれない。
『ヴァレリー』のほうは、堅実な通史的記述といえば確かにそうなのだが、序文で狙いが述べられているように、もっぱらヴァレリーの女性遍歴に焦点を絞ったものなので、思想の紹介よりも、女性関係に関するエピソードの羅列のような性格を強めている。確かにヴァレリーに関して、こうした観点でその生涯を描ききるのは珍しい試みではあるのだろうが、はたしてそこに「珍しい」という以上の意味があるのかどうかは疑問である。少なくともそれは新書に要求されているものではないように思う。副題に「知性と感性の相克」が謳われているが、その肝心の「知性」の部分がほとんど伝わってこないのが、まさに隔靴掻痒というところ。
著者の生涯などまるで存在しなかったように、思想そのものの「評伝」を描ききるようなことはできないものなのだろうか。特にヴァレリーに関して期待されるのは、そのような叙述だと思うのだが。
単なる概説に終わらせずに、しかも全体像をある程度浮彫りにする丁寧さという点では、やはりドイツ系のものの書き手のほうが上手なのだろうか。いずれにしても、ともかく共に「残念な」新書であった。
(2011. 6. 28 → II-2)
竹田壽恵雄『存在と存在者 ―― ハイデッガーとハルトマン』(創元社 1949年)
同『カント研究 ―― アナロギアの問題を中心として』(刀江書院 1950年)
一貫した見通しの下に、思想家の全体像を再構成するという意欲は、『カント研究』においても同様である。ここでは哲学における「ロゴス」の展開という観点から、カントの「超越論理」(超越論的論理学)と「アナロゴスの論理」(アナロギアの思想)の対比がなされている。前者に悟性の構成的能力を見て、『純粋理性批判』の論理を分析するのは当然だが、後者のアナロゴスの論理を『判断力批判』の反省的判断力に重ね合わせ、その両者の補完性にこそ、カントの思想の中核があるとする整理はなかなか説得力がある。この両者の混同こそ、まさに「弁証論」として論じられる問題だからである。いまとなっては言及されることも少ない『存在の類比』の著者プシュヴァラが用いられているのも興味深い。
『存在と存在者』では、ハイデガーの著書のみならず、その講義に関してもかなり立ち入った紹介がなされている。特に驚いたのが、『ソピステス』講義(1924/24)や『精神現象学』講義(1930/31)など、当時はもちろんまだ公刊されていない講義の内容を紹介している点である(ただし、著者本人が直接に聴講したのか、しかるべきルートから情報を入手したのか、定かではない。註の表記が全体として粗いので、この点は不明瞭)。加えて、グラッシの『ロゴスの優位』などにも言及されていて、その同時代的な問題意識に驚かされる。もちろん、特にハイデガーに関しては、初期のアリストテレス関連の講義録などが多数公刊された現代の資料状況からしたら、ハイデガーをプラトンに、ハルトマンをアリストテレスに結びつけることにはいろいろと反論があることだろう。しかしそうした事実関係を補ってあまりあるだけの思考の実践がここには見られるように思う。
最近は、哲学の「研究書」を名乗りながら、その実は、「研究」どころか、単なる「お勉強」ノートのようなものが多く出回る中、古いものではあっても、むしろ新鮮で読み応えのあるものだった。
(2011. 6. 26) → III-3
檜垣立哉『瞬間と永遠 ―― ジル・ドゥルーズの時間論』(岩波書店 2010年)
このところ続々と公刊されるドゥルーズ関連書籍の一冊。モノグラフの体裁を取り、標題で「時間論」という絞り込みをしているところに期待をもったが、その期待ははぐらかされた。肝心の「時間論」の基盤を作る第一章は『差異と反復』第二章の要約にすぎないし、それ以降も、時間論という視点から問題が深められるというよりは、自然史の主題や、ベンヤミン・フーコーとの近接性という話題に拡がってしまい、散漫な印象が拭えない。「バロック的時間論」なるものが提起されるが、その「バロック性」という特徴がいかなる点にあるかということも無規定のままに、連想だけが拡がっていく。西田との類似性が触れられるのも示唆的ではあるが、単なる指摘にとどまっているように思える。
そうした散漫な印象は、どの論点にも共通していて、指摘だけ、アイデアだけを読まされて、その説明がきちんとついてこないというもどかしさを抱き続けることになる。元々は雑誌に連載されたものを一冊にまとめたものらしいのだが、論文集とも言えないし、独立した「一書」とも言いがたい。各章が「論文」と呼べるほどの凝集力や論点の明確さをもっているわけでもなく、かといって、全体が「一書」といえるほどの論述の丁寧さや一貫性があるわけでなく、とにかく中途半端な印象。今後展開されるべきアイデアをメモ書きしたものというのが、一番近いところだろうか。それは文体にも反映していて、著者が独自の主張を行うところでは、修辞疑問「〜ではないだろうか」が連発され、いかにもアイデアが羅列されているだけという印象を強めてしまう。
個々の論点は興味深いものがあるし、こちらの理解不足もあるかもしれないので、多少なりともドゥルーズに親しんだら再読して、また考え直そうとは思うが、いずれにしても、書物として纏める際にはもうひと工夫があってもよかったように感じる。誰を読者として想定しているのかという点もよく見えない不思議な本ではある。
(2011. 5. 15 → II-3)
3巻本の和独大辞典の第1巻。A-Iまでだが、これだけで2500頁を超える。これまでの和独辞典の追随を許さない圧倒的な語彙量と用例を収めている。しかも単に語学的な辞典というよりは、日本文化をドイツ語で紹介するかのような面白い語彙が満載。たまたま目に付いたものを挙げると、「引かれ者」が、der vor den Richter geführte Straftäter(裁判に引き出された罪人)。日常的な用例というよりは歴史的な説明である。この付随項目に、「引かれ者の小唄」というのがあって、これがdas Liedchen eines zur Verurteilung Geführten(処刑に引き出された者の小唄)となっていて、これで意味が分かるのかと思うと、追加で一言「der Galgenhumor(ブラックユーモア)」というのがあって、これで初めて腑に落ちるという仕掛け。要するに、語源的・歴史的説明と日常的な意味の説明を両方やっているので、説明はどうしても長くなる。例えば、「花道」がerhöhter Weg durch den linken Teil des Zuschauerraums zur Bühne(観客席の左にある、舞台に向かう一段高い道)。それに加えて「仮花道」まで載っている。演目によって設けられるもう一本の花道だが、これも文字通りそのような説明がなされている。動植物の名前なども多く、日本語の項目ですら、そのものが想像できないような珍しい語がとにかく多い。
項目の語を含んだ引用文などもふんだんに取られていて、これはこれで面白いのだが、実用書としてどれだけ意味があるかは疑問。全体の印象としては、作り手が作業をしているうちにどんどんとのめり込んで、実用性や利便性などを忘れて、挙げられるものをとにかく全部挙げるということに面白さを見出してしまったかのような印象がある。そう思って眺めると、読む辞典(あるいはドイツ語による「日本事典」)としては面白い。ただ、そうなると痛恨なのが、ローマ字による立項がなされている点である。頁も多く、大型本で、しかも紙が薄いので、引くのがなかなか困難なうえに、日本語がローマ字で立項されているというのが辛すぎる。関連項目の連想が日本語的なのだから、ここはやはり五十音での立項にすべきだったのではないかと思う。
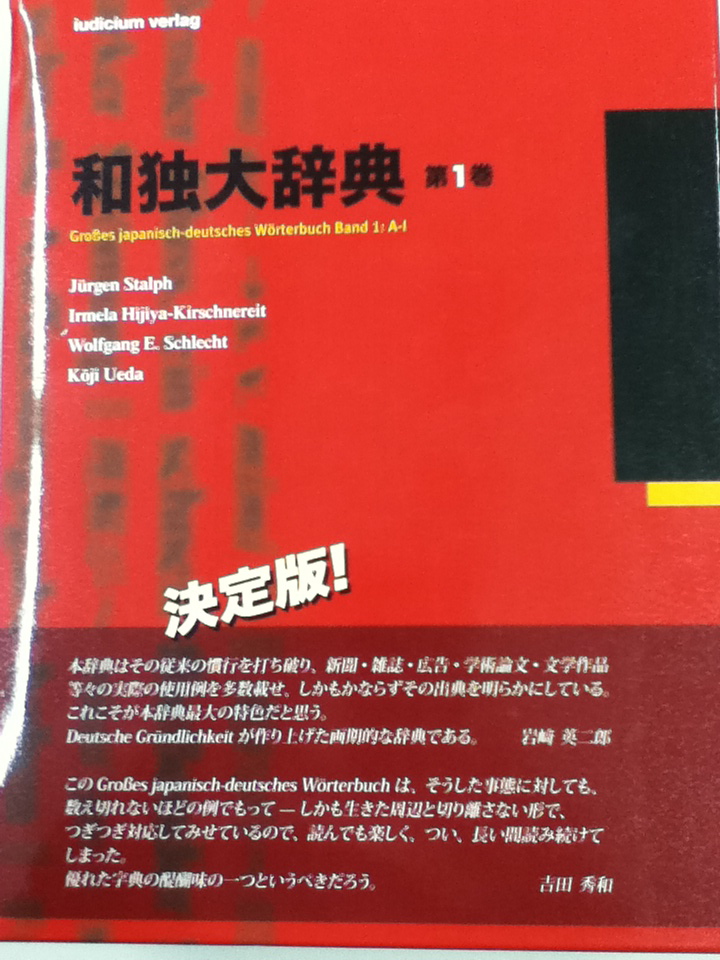
(2011. 4. 5) → I-2
J・デリダ『フッサール哲学における発生の問題』合田正人・荒金直人訳(みすず書房 2007年)
フッサール現象学を初期の『算術の哲学』からおおむね時代順に追っているが、単に客観的な発展史の記述ではなく、「発生」という問題に絞って、フッサール現象学が目指した思考を実に粘り強く追っていく。それも、フッサールの祖述に終わらず、フッサールが考えようとしたことを、自分の論述で再構成しようとしている点で、まさしく現象学の実践とも言える叙述になっている。そのために、フッサールの原典からの引用はそれほど多くない。その代わりに、フッサールが辿ったはずの思考、そしてそれを突き詰めると遭遇せざるをえない矛盾や困難を、くどいほど綿密に辿っていく息詰まる分析がなされている。
学術論文という枠の中にしっかりとどまりながら、その可能性をぎりぎりまで追いつめようとしている意志を感じる。もちろん、議論の展開の中には、のちのデリダを思わせる発想は随所に見られる。形相的・静態的現象学から、発生的現象学へ向かう流れを主題にしている点で、すでに時間性や発生、あるいは起源といったデリダの関心が現れているし、『幾何学の起源』の序文(1962年)などとも類似の議論を展開している。さらにそれを考察する方法についても、ある議論をその最後の帰結まで追うと辿り着かざるをえない齟齬を指摘しながら、それを発条にして次の論点に進んでいくという論述になっている点でも、のちに「脱構築」と呼ばれる分析法を先取りしているということは充分に見て取れる。ただ本論の中で、そうした議論に差し掛かったときにデリダが持ち出すのが、「弁証法」というフレーズであるのが、やはりいわゆる脱構築以前的な雰囲気を漂わせている。もちろん本論はフッサールが主題なので、『イデーン』についてのリクールの註解が前提になっているが、そのリクールも、しばしばこうした意味で「弁証法」の言葉を使っていたのが思い出される。かならずしもヘーゲル的な意味に限定されない、フランス的な弁証法の用例が存在して、それがやがては「脱構築」に繋がっていったような印象も受ける。
本書はおそらく、デリダという名前と関係なく、フッサール現象学の王道を歩みきった正統的研究書として受け取られるのが最もふさわしいような気がする。ヘルトの『生き生きした現在』などとともに、フッサール文献に堂々と名を連ねるべき論文であるように思える。
しかしながら、修士論文でこんな優れたものを書いたのはさすがデリダだいう評価を与え、神話化するのは考えものだろう。もちろん教育制度や言語が違うので、日本の修士論文にこれを望むのは無理があるが、議論の水準からすれば、現在の日本の博士論文には、これに匹敵するくらいのものは充分に期待して良いように思う。現代の日本のヨーロッパ哲学研究は、長年の蓄積もあって、かなりのところに来ているように感じている。ただ、このデリダの論文にあって、日本の多くの博士論文に欠けているのは、ひとつの主題を限界まで追っていくという強靱な意志かもしれない。そして、それこそが「哲学」の核心だというのも、また否めないところではあるのだが。
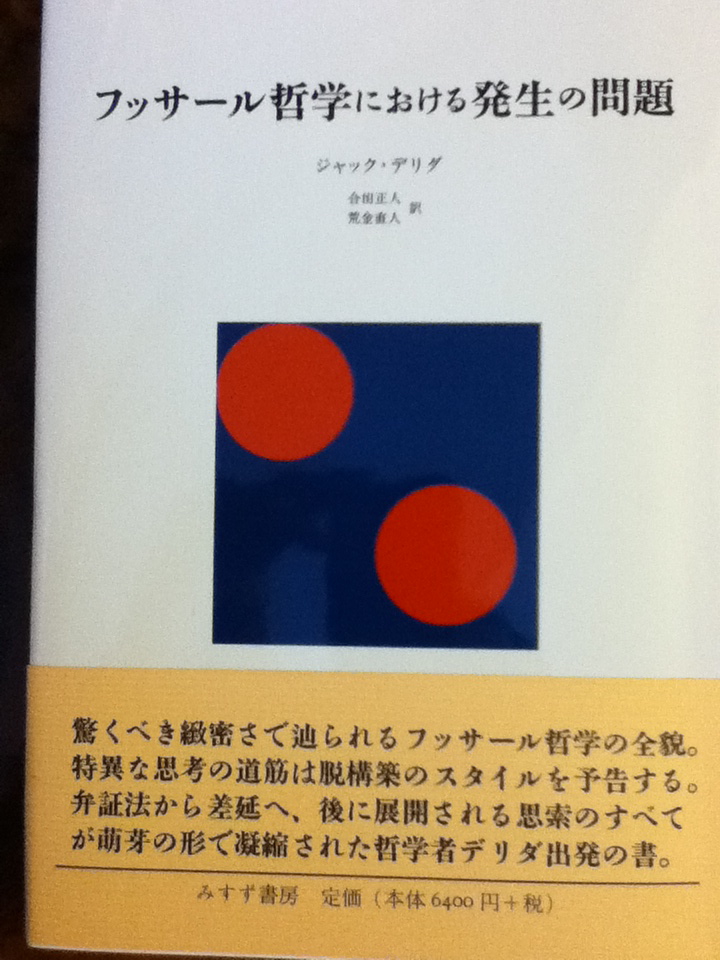
(2011. 3. 29 → II-3)
伊藤邦武『パースの宇宙論』(岩波書店 2006年)
著者の概説に従えば、パース宇宙論の要諦は、「偶然主義」「連続主義」「アガペー主義」ということになるが(112頁以下)、それは世界創造における原初の「無」を、偶然が支配する無秩序な混沌と捉え、その混沌から確率的に規則性が生起してくる過程を、論理的・数学的モデルによって描き出すことを目指している。これをパース自身は、「新ピュタゴラス主義」などと命名しているというのも興味深い(p. 100)。
パースがこうした宇宙論を展開したのは、ケーラスが主催した雑誌『モニスト』誌上でのことであった。註には以下のようにある。「ケイラスは鈴木〔大拙〕との協力関係を通じて、仏教思想、とくに『大乗起信論』にもとづく一元論的かつ汎神論的な仏教宇宙論を理解するようになる一方、鈴木はケイラスを通じて、スウェーデンボルクの思想と著作に通暁するようになり、〔......〕鈴木の親友の西田幾多郎は、ケイラスのかたわらで働く鈴木を通じて、ジェイムズ、パース、ロイスらの思想を吸収し、それを『善の研究』へと結晶させることができた。したがって、19世紀後半の『モニスト』編集部を十字路の交差点として、「西田と鈴木」と「ジェイムズ、パース、ロイス」という、日米の二組の友人哲学者たちが思想的に接触するという、非常に興味深い出来事が生じていたのである」(p. 242)。この経緯を主題としたのが、まさに下記の安藤礼二『場所と産霊』である。
もう一点示唆に富むのは、パースがこうした偶然主義的・多元論的宇宙論を展開する思想的背景として、ドゥンス・スコトゥスを指摘している点である(208頁)。これはドゥルーズのスコトゥス理解などとも重なるものだが、それがパースの中に見られるというのは、やや虚を突かれたような新鮮な指摘である。
本書は書き手の力量が際立っていて、実に読ませる。世界観的にも下記の『場所と産霊』における南方熊楠などとも近いように思える。言及されるボードレールなどの使い方も似た感性に支えられているようである。文学的な記述と論理的・数学的記述とのバランスもよく、興味が尽きない。 → II-1
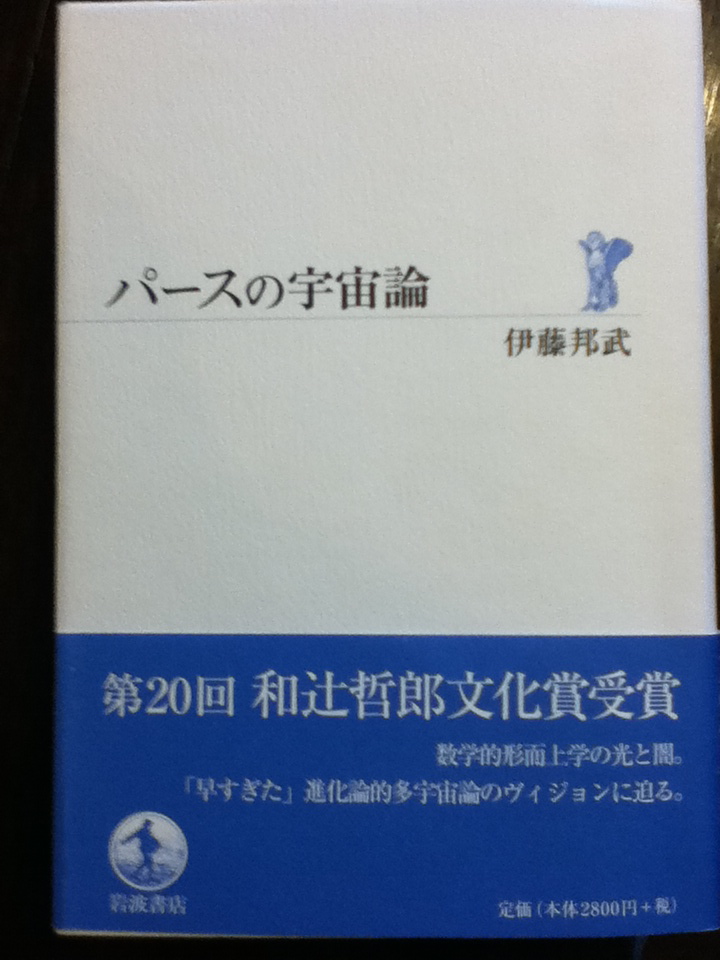
安藤礼二『場所と産霊 ―― 近代日本思想史』(講談社 2010年)
こうした19世紀末の西洋思想と日本の掛け橋となった人物として本書が焦点を当てるのが、鈴木大拙であり、アメリカ側でその仲立ちをしたケーラス、また同時期に鈴木とも交流のあった南方熊楠である。そして日本側の展開に関しては、大拙の側から西田幾多郎へ、南方熊楠から折口信夫へという流れが考察される。「場所と産霊(むすび)」という標題は、直接には西田の「場所」と折口の「産霊」を指す。本書では両者の類似、あるいは両者の思想の内に洞察される宇宙論的な共鳴を見ようとしている。その点で本書は、アナロジーとコレスポンダンスという、一歩間違うと方法論としてはかなり危ういものとなりかねない着想を手引きにしているが、ここでは、それが比較的上手くはたらいているように思える。それは本書が、単に思想的な類似性を指摘するだけに満足せず、それなりにひとつの世界観なり宇宙論的ヴィジョンを目指しているからだろう。
西田の「純粋経験」(『善の研究』)や折口の「純粋言語」(『言語情調論』)を強調するところからすると、主客未分の一元論が目指されているようにも見えるが、マッハの感覚一元論に対する大拙や西田の批判を手引きに、そうした安易な一元論から距離をとっているところもバランスが取れているように思う。大拙と西田は、「マッハからケーラスに至る感覚一元論的、受動的な仏教論を徹底的に能動化しようと試みる」(p. 251)という指摘は重要である。
補論として付された南方論の以下の指摘も有益。「〔南方にとって〕曼荼羅を理解するための知識は、<物>の外側から与えられる網羅的な<博識>ではなく、<物>同士の複雑な関係性の内部から生成されてくる自然発生的で流動的な知識、<自智>でなければならなかった」(p. 260s.)。まさに「言葉」と「物」の分離に抗い、一旦はその分離を経たうえでもう一度自らのうえに折り返り、言葉と物との複雑なネットワークを形成する思考が簡潔に示されている。「燕石考」を手がかりに、レヴィ=ストロース流の「神話論理」を導出する論述は、短いながら説得力がある(「石が語る ―― 南方熊楠の「神話論理」」)。 → II-3
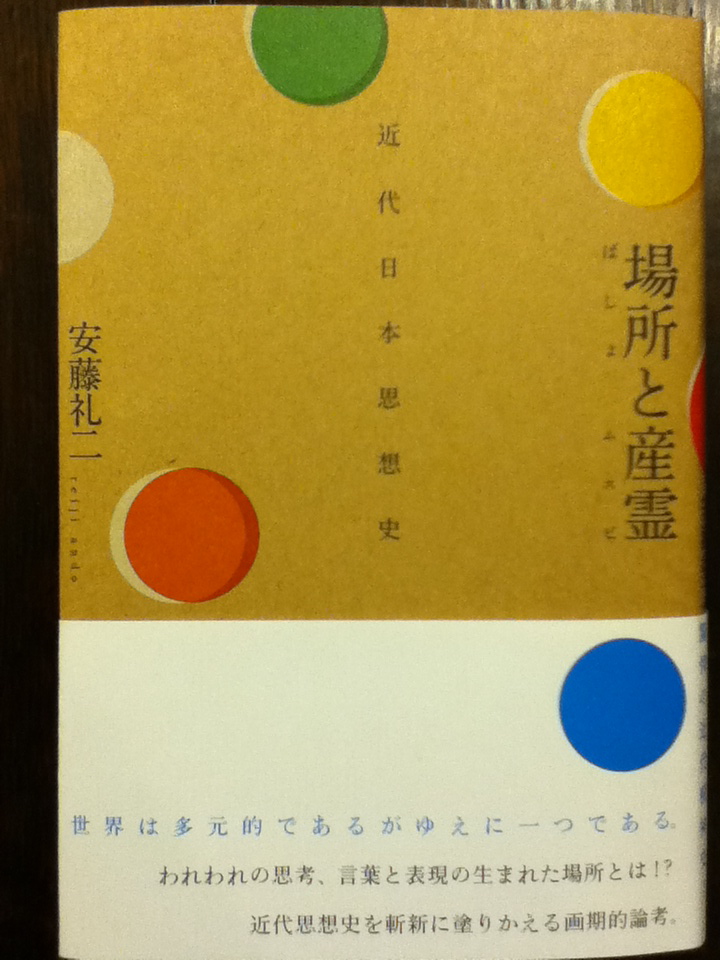
本書は本文が亀の子文字なので、ところどころに潰れてしまっているような個所があるが、このシリーズのなかではまずまず許容範囲。以前、Voss訳の『イーリアス』をこのNabuで手に入れたことがあったが、これなどは裏の頁が透けて裏映りしてしまい、それがデータとしてそのままプリントされたので、亀の子文字が二重写しになるというとんでもない品質になっていた。廉価さの代償なのだが、時には頁が飛んでしまっているようなこともあるように聴く。その点では、このクレメンスのものは、一応は読むのに支障のないレベルなので安心した。
→ IV-4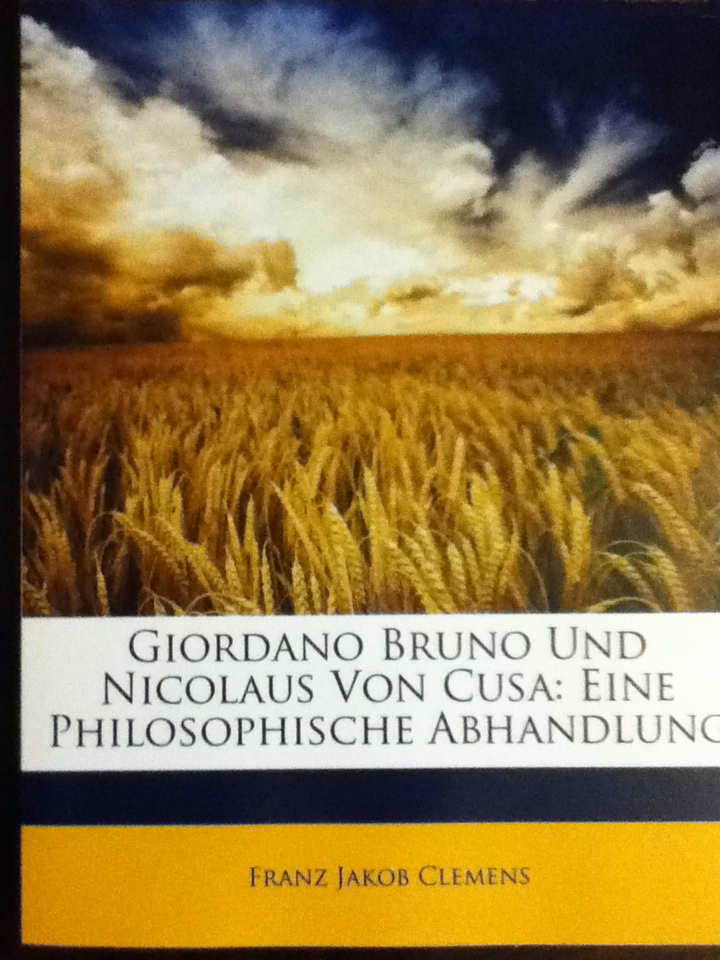
大澤真幸『量子の社会哲学 ―― 革命は過去を救うと猫が言う』(講談社 2010年)
標題にも示されているように、本書の狙いは「量子力学を......同時代の社会科学、哲学、芸術、政治革命的運動等と自由に関連づけること」にあるとされる。かといって、間違っても廣重徹『科学の社会史』のような優れた試みを期待してはいけない。本書は、近代以前から現代にかけてのきわめて長く複雑な思想的経緯を、至極単純かつ抽象的な図式によって外在的に整理しようという試みなのだから。
実のところ、本書をどう紹介したらよいのかが分からないというのが正直なところである。量子力学に関するきちんとした理解が得られるわけでもなければ、哲学・芸術・政治学に関して、独自の創見が示されるわけでもない。物理学・哲学・芸術・政治に通底する同時代的な精神を浮彫りにすると言うと聞こえはいいが、要するにそれは、あらゆるものを横滑りに繋げて、比喩を比喩によって説明するというだけのことにすぎない。賢そうに見える論法は身につくかもしれないが、思想的に発展性のある示唆がそこから汲み取れるわけでもない。
例えば、量子力学とキュビスムが思想的に「平行」しているという議論に関して、こんなふうに語られる。「キュビスムは、対象を同時に把握する、複数の異なる視点を前提にしている。......量子力学においても、「(対象における)知」は、常に、複数の(二つの)場所に分裂し、同時に帰属する形で与えられる。単一の超越的な視点を崩壊させる、こうした視点の多数性に関して、量子力学のキュビスムは共通しているのである」(p. 145)。一応気の利いた比喩とは言えるが、それ以上に本質的な洞察や思考を駆り立てることのない指摘である。
さらに政治・科学・精神分析の共通性に関してはこんな文章がある。「シュミットの決断主義は、量子力学的な観測 ―― 波動関数を崩壊させるあの観測 ―― に対応している。観測は、政治的決断主義の物理学的な表現である。そうであるとすれば、フロイトのMM〔『モーセと一神教』〕もまた、量子力学と同じ精神を共有していることになるだろう。TT〔『トーテムとタブー』〕からMMへの転換は、相対性理論から量子力学への転換を導いた精神の転換のもう一つの現れではないだろうか」(174頁)。ここまでくると、何をかいわんや。
という次第で、本書をどう評すればよいのか、困ってしまうのだが、あえて言うなら、「思想的小噺集」といったところだろうか。異質なものを結び合わせることで笑いが生まれるということはあるだろう。しかし、それにしても32章ものあいだ、のべつそれを繰り返されると、もはや笑う気力も失せてくる。著者がひたすら繰り返す「同型性」や「同じシステム」という言葉だけが虚しく響く。おそらく30年ほど前なら、この種の議論も、フーコー「風」の試みとして、その抽象性や形式性が評価されかもしれないが、いまとはなってはひたすら困惑の種となってしまう。「Aという思想とBという思想が論理的には同型的である」 ―― 「だから何?」という自問自答が著者のなかでまったくなされていないのが、本書全体の言い知れぬ緊張感の欠如の原因だろうか。
この著者には以前からそうした懸念を抱いていたが、それは別段この著者ひとりの問題ではない。やはり考えてみなければならないのは、非専門家の怖さというものかもしれない。専門家なら、自分が専門としているある対象を別の対象と比較する際には、臆病なくらい慎重なものだが、それは自分が親しんだ対象に関する一種の質的な手触りのようなものに忠実だからだろう。その意味では、思想をその間近で捉えるものは、文体や思考を含めた物質的なものに絡め取られる唯物論者にならざるをえないのである。こうした感覚が、専門家の狭隘さを産むのも事実なのだが、それは思想的に深く考えるためには避けがたい制約のようにも思える。
本書に見られるような、評論的で、妙に物分かりのよい解説書というのは、おそらくその辺りの質感を犠牲にして、すべてを横並びに眺めた結果、表層的な類似と図式によって読者を強引に納得させてしまうということになるのだろう。純然たる専門家向けでもなく、かといって平板で概説的な理解を列挙するのでもない高度の思想書というものが、いかに困難であるかをあらためて感じる。
(2010. 2. 14) → IV-4
田口茂『フッサールにおける<原自我>の問題 ―― 自己の自明な<近さ>への問い』(法政大学出版局 2010年)
「原自我」とは、経験的な自我とは一致することがない超越論的な次元であるが、それでもなお、その超越論的な眼差しが一種の「眼差し」である限りでもたざるをえない視点性を有している。その意味でこの「原自我」は、「自我」としての限定性と、「原」という根源性という、矛盾する課題を二つながらに抱え込んだ、それ自体が逆説的な名称である。そのために、本書の最後の議論は、「原自我」の中に現れる「自我」ならざる位相へと踏み込んでいかざるをえない。とはいっても、その異他的な位相は、けっして外部から自我にやってくるのではなく、自我の中で自我が反転する極限値として示されるほかはない。つまりそこでは、現象学が自らの格率としてきた「視る」ことが、自らの虚焦点を「視て」しまうという不可思議な事態、あるいは「視る」ことが挫折することによって「視る」行為が作動し始めるという逆説に直面することになる。
本書の特色は、何よりもその一貫した叙述にある。現象学の入門書にはかならず「事象そのものへ」というフッサールの銘が引用されるが、現象学関連の多くの著作は、それにもかかわらず、きわめて外在的な「解説書」になっていることが多い。その点では本書は、凡百の現象学入門書には見られない事象への忠実さが全編を貫き、読者も「現象学する」という哲学の遂行態の中に共に入り込み、共に思考するという稀有な経験を味わうことができるだろう。最終的な「異他性」の議論にしても、いたずらにレヴィナスやデリダなどの「現代思想」に愛想を振りまいて、適当な結論をつけるというのではなく、あくまでも現象学的な思考を徹底したらどのようにならざるをえないかという点を粘り強く考え続けていく姿勢が崩れることがない。けっして派手な論点ではないが、地道に現象学(あるいは哲学)を考えようとする読者にとっては得がたい著書となるだろう。文体も、その議論をトレースするに相応しく、足腰が強くて息が長い、それでいて透明度を失わない文章になっていて、見事である。
(2011. 2. 12.) → II-1
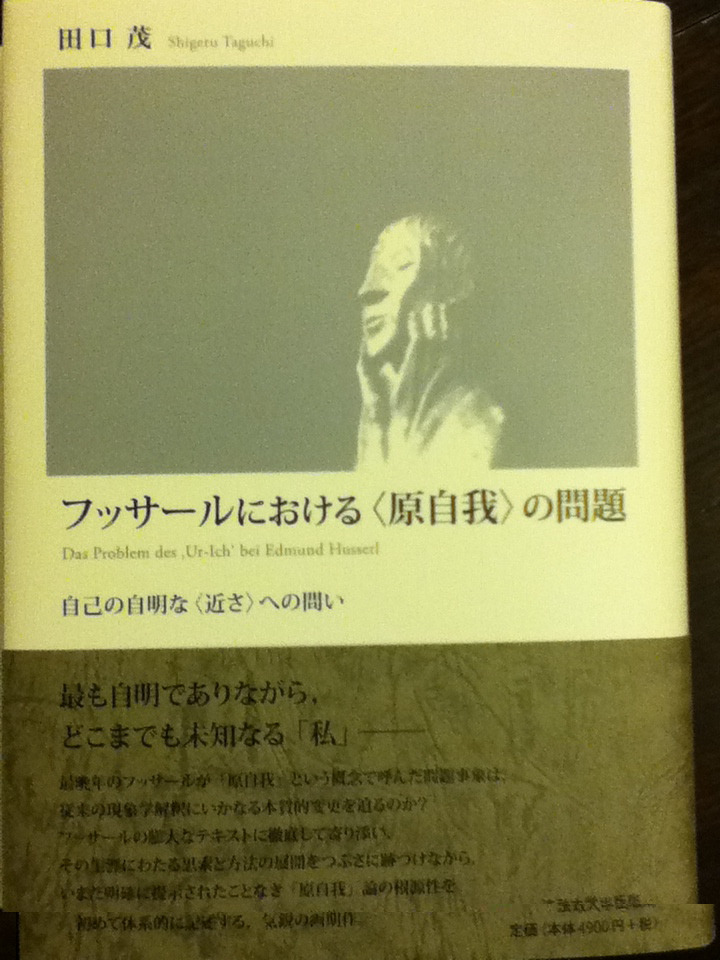
書物の電子化によって起こる事象は、かならずしも現代に始まったことではなく、情報伝達の迅速化など、17世紀でさえも驚くべきものがあるといった長いスパンの議論によって、現代の優位にのぼせ上がったり、いたずらに危機感を抱いたりすることなく、現代固有に思われる事柄を相対化する効果はあるだろう。しかし、電子出版やパブリック・ドメインの爆発的増加は、特に人文学にとっては大きな影響と変質を与えるのではないかとも思えるのだが、その辺の見通しもお世辞にも具体的とは言えない。やはり功なり名を遂げた高名な学者が状況をのんびりと眺めているといったところか。アマチュアとプロの境界の消滅(逆に言えば、プロの牙城である大学の意味の減退)など、この環境によって起こってくる事柄は、やはりそれほど小さくはないと思えるのだが。
所有している古書自慢にしても、キルヒャーの古書に触れられるくだりなど、これでここに『プロスペローの本』でキルヒャーなどのバロック図譜を大量に用い、自身も蔵書家と聴く映画監督のグリーナウェイでもいれば、書物とメディア全般をめぐる刺戟的な話題が展開されただろうにと思ってしまう。さらに、紙のメディアの実力を見せつけるために、言及される書物の書影や図版があってもいいと思うのだが、そうした編集上の工夫もない。ただ、書物の外見はなかなか心地よく、三方金ならぬ三方青という独特の風合いも面白い。ということで、その物質的な魅力から購入してしまったが、内容的には特にもっているまでもないかもしれない。これならば、例えば今福龍太『身体としての書物』のほうが読み応えがある。
(2011. 2. 5.) → Book

本書の各論考で提示される主題は、それぞれに興味深いものがある。ロマン主義の「断片的思考」とニーチェ的アフォリズムのスタイルとの対比は、20世紀の脱構築に繋がるものであるし、「パラバシス」という修辞学用語によって暗示される「中断」の思考は、有機的「連続」や地平の「拡張」に依拠する哲学的解釈学とは異なった文献学を示唆する。「実体」のパラダイムから「過程」の思考への移行は、生成や差異を主題とする現代哲学の動向にも沿うものだろう。
とはいえ、本書ではまだそれらの考察は緒に就いたばかりといった印象は拭えない。どの論考も(個々の割り当ての分量が少ないということもあって)、問題の出発点を示して、「ニーチェとシュレーゲル」という主題の正当性を主張することで精一杯といったところがあって、その対比が哲学的にどのような新生面を切り開くかという点にまでは及んでいない。今後の展開に期待したいが、主題を明示してくれただけでもひとつの功績だろう。
ちなみに本書は、故エルンスト・ベーラーに捧げられており、「ニーチェとシュレーゲル」という類似性を最初に指摘した功労者としても彼が言及されている。それは確かにそうなのだが、私自身はベーラーが書いたものに感心した記憶がない。いかにも凡庸な印象を抱き続けたが、どの分野でも、凡庸な大家というのは、その領域を普及させるには必要な存在なのかもしれない。
(2011. 1.5) → I-2

リスト:2009/10年, 2008年, 2007年, 2006年, 2005年, 2004年, 2003年, 2002年(2), 2002年(1)